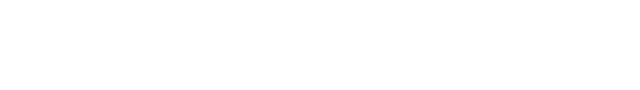急性心筋梗塞による心原性ショックの治療ーECMOの効果は?ー
急性心筋梗塞の患者さんを救命するためのkey pointはみっつあります。ひとつは患者さん自身が自覚症状(胸部圧迫感、胸部絞扼感、呼吸困難、失神など)に関して、これはただならないこと、と認識して、一刻も早く119 callをすることです。私は危険因子(高血圧、糖尿病、高コレステロール血症)があって、男性で35歳以上、女性で50歳以上の患者さんには、10分以上、胸痛が続けば、ためらわず119 callとお話ししています。ふたつめは入院前に不幸にも致死的不整脈(心室細動と無脈性心室頻拍)を合併した例への胸骨圧迫と迅速な除細動(AEDの活用)を施行することです。みっつめは入院後は少なくとも90分以内に閉塞した冠動脈を再開通させることです。心筋が壊れる範囲(壊死する範囲)を小さくすることにより、心機能の低下を抑制し、ひいては生存率を向上させる、退院後の社会生活を問題なく営めるようにすることが、再開通治療の目的です。
AEDに関しては、2016年までの統計データでは順調にその販売台数を伸ばしています。一方、一般市民による心停止例に対するAED施行例数は2019年の2168例をピークにむしろ減少に転じ、2021年の施行例数:1719例でした(令和4年版 救急救助の現況:kkkg_r04_01_kyukyu.pdf (fdma.go.jp)。AEDの設置場所の増加にも関わらず、市民によるAEDの施行例が増加しない一因はAEDを操作することに対するためらい、怖れが市民=非医療者にあるためと思います。
急性心筋梗塞の院内予後の改善は再開通治療の普及と薬物治療の進歩により、緊急カテーテル治療が可能な病院での急性期の死亡率は5-7%程度であり、病院まで到達できれば90%以上は助かる病気が心筋梗塞といえます。しかしながら、その予後の改善に関して、ここ10年以上は足踏み状態なのです。それは、なぜか?心原性ショックのため、です。心原性ショックは入院後の急性期死亡の第一の原因であり(二番目は心破裂)、ショックに対する従来の治療方法に比べて、より効果的な治療を見いだしていないため、結果として足踏み状態が続いています。
近年、心原性ショックの治療方法として、注目されてきた治療装置があります。それがECMO(ExtraCorporeal Membrane Oxygenation:体外式膜型人工肺)です。ECMOは広範な心筋梗塞のために不足する心拍出量を補う効果と血液の酸素化を得る効果を期待できます。血流の途絶もしくは低下により傷害された心筋が収縮性を回復できるまでの時間稼ぎが治療の狙いです。
2023年の欧州心臓病学会(ESC)にて、心原性ショックを合併した急性心筋梗塞に対するECMOの効果を検討した臨床研究が報告されました。この研究は同時にNew England Journal of Medicineにも掲載されています。ECMO施行群:208例と非施行群:209例の間で、効果の指標として入院後30日の死亡率、人工呼吸器の施行期間などを検討しています。また、安全性の指標として、中等症―重症の出血の頻度と手術またはカテーテル治療を要する末梢血管の血行不全の頻度を比較しています。対象例の特徴として77.7%の人が心肺蘇生術を施行されており、また、95.4%の人に意識障害を認めていることから、心原性ショックの中でも最重症といえる例が検討の対象となっています。
入院30日後の死亡率はECMO施行群:47.8%、非施行群:49.0%と2群間での差異を認めませんでした。一方、中等度―重症の出血の頻度(23.4% vs. 9.6%)、末梢血管の循環不全の頻度(11.0% vs. 3.8%)とECMOにより合併症の頻度が明らかに増加しました。
まとめると心原性ショックを伴う急性心筋梗塞に対するECMOが生命予後を改善することはなく、むしろ合併症の頻度を高めるという残念な結果となりました。この理由として著者らも述べていますが、ECMO施行例では中等度以上の出血の合併症、および末梢血管の血流障害(主として下肢虚血と思います)の頻度が多いことが、ECMOの良好な効果を打ち消しているのかもしれません。
心原性ショックの予後を改善させる有効な治療法が見出しがたい、現在、病院到着前の救急が極めて重要と思います。すなわち、患者さん自身が自分の症状(胸痛、呼吸困難、失神など)に関して、心臓病かもしれないと思って、119 callを行う事、胸骨圧迫(心マッサージとAEDの実技の啓蒙を今よりも普及させることが、急性心筋梗塞に伴う心原性ショックの合併頻度を減らし、ひいては予後を改善させることにつながるかと思います。
参考文献
N Engl J Med 2023; 389:1286-129